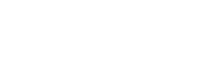『機械仕掛けの愛1』業田良家
-
「ロボットに心はあるのか。人間が主観的に感じているのと同様に、ロボットには自ら思考して答えを出す、心のようなものがあるのか。機械だけあって単純に、積み重ねられた膨大のデータから取捨選択して、反応しているだけに過ぎないのか。たとえ反応に過ぎないのだとしても、それが人間の心の動きといったいどう違うのか。そもそも人間の心とは何なのか。小説や漫画や映画やアニメーションといったジャンルで多く描かれ、様々なバリエーションが生み出されている、ロボットの心という命題を含んだ物語。これに、「自虐の詩」などの作品を持つ漫画家の業田良家が挑んだのが、「機械仕掛けの愛1」(小学館、524円)という連作集。現れたのは、人間に似て非なる存在としてのロボット、人間に従い人間を助けるロボットを一種の鏡に見立てて、人間という存在の特質を浮かび上がらせようとした物語たちだ。冒頭の「ペットロボ」というエピソード。子供代わりに育てたロボットを、他のが良いからと売り払う人間の姿が、生んだ子でも邪魔なら捨てられる昨今の風潮、希薄化する人と人との繋がりを想起させる。その上で、大切にしてくれた人を思い続けるロボットの健気さと、かつて共に暮らした存在を家族と認める人間の優しさを示して、繋がりとは何かを思い出させて読む人たちの涙を誘う。ロボットに心はあるかもしれないし、ないかもしれない。ただし、人間には確実に心がある。優しかった母親を慕う少女のロボットの姿に
涙し、少女と母親を思い続けるロボットに同情し、ぎくしゃくしていた息子と母親との関係を、どうにか修復しようとするロボットに愛おしさを感じることができたとしたら、それは人間の心が見せたものだ。そうやって得られた感情を、今度は世界の大勢の人たちに、心を感じることもできない苦境に喘ぐ人たちに、向けて出していくことが、「機械仕掛けの愛」を読み終えた、心を持つ人間の使命だ。」