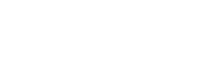選考作品へのおすすめコメント
マンガ大賞2016一次選考作品
『赤白つるばみ』楠本 まき
-
「これまでの作品も含めて、楠本作品は絵柄やファッション・名前などが独創的であることに意識が向かいがちだけれど、本作は非常にまじめに直截的に「人と少し違う」人たちの生き方を描いている。帰国子女でクラスで浮いていた少女、性別に相応しいとされる恰好を強いられることに反感を持つ双子、色弱の少年、色聴の老女、イマジナリーフレンドのいる少女。そういった「人と少し違う」人たちが主役の青年二人を中心にして、物語の中でたくさん出てくる。みんなが少しずつ人と違って、その中でその違いに一喜一憂したり、その違いとは全く関係ないところでも一喜一憂したりしている。みんながそれぞれ人と違うところを持っている人間で、相互の理解や歩み寄りによって傷つけあわずに過ごせるという希望を匂わせている反面、現状ではそれが難しいことも描いている。ある、「人と少し違う」少女は、自分が人と違っていることを知っている。そのことを口に出さず、空気を読んで過ごそうとしている。そういう少女ですら、他の「人と(自分と)少し違う」少女について、その違いゆえに陰口を叩いている。それが現実だ。それ以外にもこの世界は、レイシズムやセクシズム、弾圧や殺戮に満ちている。いやになるくらい世界は陰惨で、死に囲まれている。けれど終盤、陰口を叩いていた少女は、自分の「違い」がほかの人にもあると知り、嫌っていた少女に少し心を開く。彼女の秘密を知ったわけでも、何か大きな理由があったわけでもない。ただ、少女は後天的に他人に寛容になった。そうやって人は変わることもあるし、譲歩することもできる。そういう少しの希望があるからこそ、人は生きてゆける。直球だけれど余韻があって、独特の間や美しい線が画面いっぱいに広がっている。楠本まきにしか出せない雰囲気がある。」