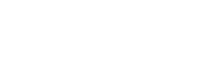『取水塔』粟岳高弘
-
「これは凄い。とても凄い。とてつもなく凄い。粟岳高弘の『取水塔』(駒草出版)は、いつもの如くにぬぽぽんとした顔立ちやスタイルを持った女の子たちが登場しては、セーラー服だったりスクール水着だったり裸だったりになって、歩いたり走ったり泳いだりする姿を存分に味わえる漫画になっている。けれども、そこに描かれているのは、とてつもく遠大な時間を経て実現した、異星人と地球人との関係。つまりはコンタクトの物語。SFとして古今の東西で描かれたテーマを、ぬぽぽんとした画風の中にきっちりと表現してみせた、粟岳高弘ならではの作品になっている。冒頭、海岸縁に広がる地帯に散在する、謎めいた物体が登場する。グニュグニュとしてアメフラシのような生物にも見えるそれらだけれど、女の子たちが容器に集めると集まって大きくなってぬめぬめと動く。 本当に生物なのか。別の何かか。そんなエピソードをプロローグにして紡がれていく物語の中で、それらの正体がだんだんと見えて来て、女の子たちの血筋的に受け継がれた力と、与えられた使命ようなものも分かって来る。そして、異種生命体との交流があり企みが暴かれ、グッと宇宙が近づいて来るストーリーが繰り広げられるけれど、ここで面白いのは、そうした人類史にも残るようなプロセスに、大人たちとか政治家とか、軍隊とか正義の味方といったものを表向きには関わらせないこと。近隣に暮らしている女子高生たちをメインに、というよりほとのど彼女たちに全面的に頼らせ、関連する一族の大人たちは、女の子たちがやろうとしていること、起こしてしまったことのバックアップに回らせて、あまり表に出さない。舞台となっている場所も、静岡県は菊川とか掛川とか牧ノ原台地あたりを一体とした東遠地域を中心にした地域。そして背景も、遠州灘が広がる海岸と、茶畑が続く平地とそして小高い山くらいに絞ってあって、住宅街とか商店街とか、駅とか役所とかショッピングモールといったものは描かれない。だから読んでいて、どことなく箱庭的な雰囲気が感じられる。ぬぽぽんとした絵柄と相まって、のほほんとした日常がつづられる。けれども、そうやって淡々と紡がれていく展開には、とてつもなく壮大にして深淵な接触の物語が込められている。海岸からちょっとだけ離れた海の中に立つ取水塔があり、そこから伸びるように字面の下を通って続く通路があり、くぐって入り込むと得体の知れない土塊があって、だんだんと集まりやがて動き出してそして言葉も解するようになっていく。謎めく物体との接触から、それらの目覚めを経てクライマックスへと向かっていく展開には、とてつもなく壮大にして深淵な接触の物語が込められている。それは文字通りに宇宙的なスケールを持ったのだけれど、ハリウッド映画にあるようなスペクタクルなシーンはほとんど描かれない。臨む高草山からのビームのような攻撃も散発的で、苛烈なサバイバルといった雰囲気はない。日常にちょっとだけ不思議が混じった光景の中を、淡々と進んでいくストーリーの上で、少女たちや少年たちが自分の力で謎に迫り、秘密を解き、問題を乗り越えていく姿を眺めつつ、いったい何が起こっているんだろう? といったことをじわじわと感じ、噛みしめるようにしてい読んでいける。背後で社会がどう動いているかも含めて想像する楽しみもある。広がりというよりも、奥行きを持った作品だと言える。同じ作者の単行本『いない時に来る列車』の表題作は、滅び去ったような世界で切り取られた断片から、追い詰められた今を確認しつつ、そこから未来へと可能性を探っていくような話になっていた。単行本の大半を占めていた「斥力構体」のシリーズは、「取水塔」と同じ東遠あたりを思わせる地域を舞台にしながら、現実が異次元と背中合わせになって、不思議が日常となった世界に生きる少女や少年たちが描かれていた。『取水塔』の場合は、もっと現実に近づけつつ、そこに重なった非日常を描いて少女たちに難題を突きつけ、それを乗り越えていく楽しみを感じさせる物語になっている。噛みしめるように味わいながら、だんだんと進んでいくコンタクトと、その先に起こるかもしれない事態にワクワクできる。やがて訪れた結末で、自分なら何を選ぶのか? といった思いにとらわれるはずだ。これだけの構想を物語にして描き、同人誌で淡々と描き続けて、これだけのボリュームをもった作品にした作者の努力と根性に、惜しみない喝采を。何よりもその才能に賞賛を。」