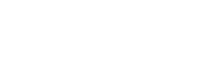選考作品へのおすすめコメント
マンガ大賞2018一次選考作品
『弟の夫』田亀源五郎
-
「娘と二人暮らす男のもとを、亡くなった弟の『夫』を名乗るカナダ人男性が訪れる。弟の夫。同性婚が許されたカナダで、弟はカナダ人の男性と結婚して家庭を作っていたのだ。ということで始まる日々のお話。突然身近に現れた同性愛者相手にどう振る舞えばいいの? という混乱と拒絶と許容のさまを、共感しやすくて、かつ「きわどい」ところまで切り込んでいくのが面白い。「きわどい」というのは、例えば何も知らない幼い娘さんに、同性同士が結婚するのはどういうことなのか、どういう意味があることなのかをきちんと教えなければならないということだ。なんらかの性癖を元に人を差別することあるいは差別しないことは、良いことなのか悪いことなのか、そしてそれはなぜなのかを、自分の言葉で考え伝えなければならないということだ。そういう「きわどさ」、唐突に突きつけられる、繊細で真摯な思考の是非。それが面白い。しかしそれよりも、ここで描かれているのが、本質的に「親しい人を喪った喪失の哀しみ」であることが好ましい。胸を打つ。親しかった人、あるいは、もっと親しくなれたし、もしかすると、もっと親しくすべきだったかもしれない人。しかし、その人は、もうこの世のどこにも居らず、そのような機会も永遠に失われたのだ、という喪失の哀しみ。それが、切々と描かれることに好意を覚える。沁み入る。我々は、それぞれが、それぞれに、それぞれの事情を抱えながら生きるしかねえのだ、という当たり前のことが、ほんのりと希望をもって肯定される。たいへん良い。」