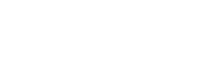選考作品へのおすすめコメント
マンガ大賞2024一次選考作品
『かみまち』今日マチ子
-

-
「一晩の雨風をしのぐ部屋を提供してくれる『神』をただひたすらSNSで待つ家出少女たちのリアルを描く上下編。娘への愛情の名の下にモンスターのように拘束してくるママから逃げるため。愛情が足りないママが連れ込む男の汚れた手から逃げるため。などなど『かみまち=神待ち』の境地に至る十代女性の理由はそれぞれながら、しかし、そうするしか生きていけない、ほかに生き延びるよすががない彼女たちはたどり着くべくしてそこにたどり着いた。神などと言ってみたところで実態は欲望をギラつかせて彼女らを搾取しようとする、世代を問わず薄汚いただの男だ。だから『神』という言葉はそんな男たちの本当の顔を糊塗しているというわけではもちろんなく、『救いの神などこの世にいない』という彼女らの皮肉だし、自らの境遇に向けた絶望の表現だ。つまり呪詛。ただの男性読者である私は読み進めながら、彼女らに居場所を提供することさえしない無関心極まる日本社会について憤ってみたところで、『で、そういうことを思うあんた、自分はどうなのさ?』という問いかけとたびたび向き合わざるを得ない。読んでいてとてもつらい。作者自身も後書きで『とにかく気分が塞ぎがちだった。でもやめる気もなかった』と書いている。社会に対する冷たい怒りを感じる一作。」