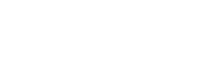『今日も吹部は!』宮脇ビリー
-

-
「吹奏楽は格闘だ。そんな訳はない?だったら宮脇ビリーの『今日も吹部は!』(小学館)を読むと良い。ギャルな部長と眼鏡の委員長風な副部長が殴り合っては何かの決着を付けようとしている。トランペットのパートでも部員が殴り合い蹴り合って主義のためにしのぎを削り合っている。部長と副部長の場合はまだ、吹奏楽部の方針を全国大会で金賞を目指そうとする、ユーフォニアムが響いているような吹奏楽に関わる対決だからまだ良いけれど、トランペットのパートの殴り合いに蹴り合いは、部長と副部長とのどちらが受けで攻めなのかといった見解の相違によるもの。その重大性は大いに分かるけれど、しかしやっぱり吹奏楽とは関係ない。というより『今日も吹部は!』を読んでも、吹奏楽が奏でられているような場面はなかなかない。あるのは部員たちが会話したり殴り合ったりしているような場面ばかり。あるいはクラリネット吹きの男子部員が使っているリードを手に入れたいと後輩の女子部員が望む場面なり、一見ひ弱そうに見えるトランペットの先輩の女子が実は元ヤンで合気道の達人で元野球部のエースすら投げ飛ばす場面なりといったもの。演奏からはほど遠い。けれども面白い。そして吹奏楽味もある。どこに? というのはつまり吹奏楽部で表がコンクールを目指す猛練習なら、裏にある部員たちの日常であり感情であり関係がしっかり描かれているということだ。どのような興味を持って吹奏楽部に入ってきたのか。どのような関係で吹奏楽部内の諸々な事柄が進んでいくのか、等々。そうしたことは例えばユーフォニアムが響くような小説なりアニメにはあまり描かれない。鬼のような顧問の下で巧くなりたいと頑張る女子部員の話がほとんど全編を覆っている。そんな女子部員にも恋のドラマはあって、他の部員が絡んだもやもやとした関係が描かれても、大きく発展してギクシャクとしてギスギスになって瓦解するような展開にはならない。そして、吹奏楽そのものにまるで影響は出ない。そんなはずはないのだ。音楽がメンタルに左右されるならそこに何かしらの影響は出るものなのだ。人が音楽を奏でる以上、人の感情や関係も音楽に現れる。そうした状況の片面を『今日も吹部は!』は描いた物語なのだ。片面がいつ描かれるのか、本当に描かれるのかの予想がまったくつかないことは別にして。野球部のエースで学校を甲子園まで連れて行った汐見草太郎が、世をはかなんで屋上で黄昏れていた時に、小松原ルーシーから声をかけられ吹奏楽部に引っ張り込まれる展開はなかなかに珍しいものだ。エースならきっとバッターとしても四番で投げられなくても走れなくても活躍できそうなものなのに、そうはせず吹奏楽部に入って右も左も分からない吹奏楽の世界で頑張ろうとする汐見の姿に、スポーツマンのセカンドキャリアの可能性が浮かび、あるいは道はどこにだって続いているという格言めいたものも浮かんで、同じように挫折を味わっている人に希望を与える。そうして入った吹奏楽部で女子が殴り合っている姿を見るのもひとつの経験。そこから野球部では絶対に出会えなかった人たちに触れ、考え方も知って成長していくドラマを見せようとしているのかもしれない。だったら吹奏楽でなくても良い? そこはそれ、いつかきっとやっぱりどうにか吹奏楽そのものにも描写が及んで、やる気のある部員もない部員もどっちでもない部員もまとまって、全日本音楽コンクールで金賞をとるような活躍を見せてくれるだろう。くれないかもしれないけれど。」